画面で見るマニュアル



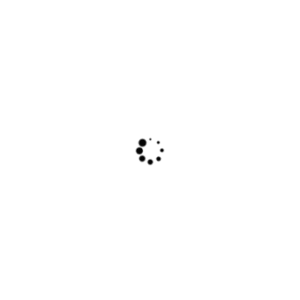
画面の縦横の比率(アスペクト比)を設定します。
フルスクリーン
映像を画面全体に拡大表示します。
画面の縦横の比率が変わってしまう場合があります。
固定
映像を画面の縦横の比率を保持したまま、最大の大きさで表示します。
映像の上下や左右に映像が表示されない部分ができる場合があります。
・ 最大解像度(3840×2160)で表示しているとき
・ PIP/POPを有効にしているとき
映像はなるべく、最大解像度(3840×2160)か、液晶ディスプレイの画面と同じ画面の縦横比(16:9)にしてください。
画面の輝度を調節します。
⇒ 用語解説:輝度
映像の明暗比を調節します。
映像の色味の明るさを調節します。
映像の鮮明度を調節します。
※ 最大解像度で表示している時は、調節できません。
[オン]にすると、画面表示の応答速度を向上します。
※ PIP/POPを有効にしているときはこの項目を選べず、この機能は働きません。
・ 垂直周波数(リフレッシュレート)が60Hz以外の映像を表示しているとき
・ 設定メニューを表示しているとき
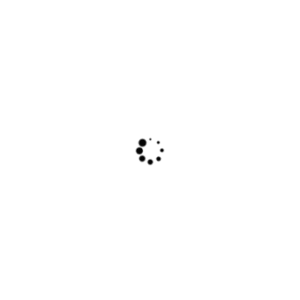
子画面の表示・モードを設定します。
※「デモモード」が有効の場合、子画面を使えません。
子画面にどの入力端子の映像を表示するか設定します。
子画面の大きさを設定します。(PIPのみ)
子画面の位置を設定します。(PIPのみ)
親画面と子画面を入れ換えます。
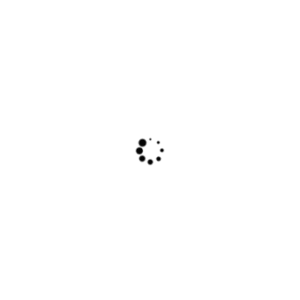
音量を調節します。
[オン]のときは、音声がスピーカーから出力されません。
どの入力端子の音声を出力するか設定します。
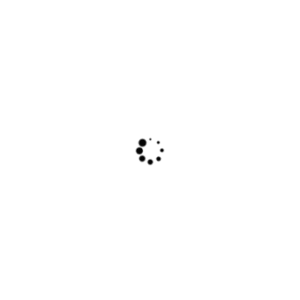
⇒ 用語解説:色温度
色温度を6500Kに設定します。
色温度を7200Kに設定します。
色温度を9300Kに設定します。
赤緑青の各色を調節します。
画面から出るブルーライトを低減する度合いを調節します。
映像の色相を調節します。
※ HDMIで入力した場合だけ有効です。
⇒ 用語解説:色合い
映像にメリハリを付け、鮮やかに表現するエンハンストカラー機能を調節します。
本製品のバージョンが古いです。
弊社サポートライブラリの本製品のページをご覧になり、本製品をバージョンアップしてください。
バージョンアップ前の機能内容
映像の色の濃さを調節します。
※ HDMIで入力した場合だけ有効です。
⇒ 用語解説:色の濃さ
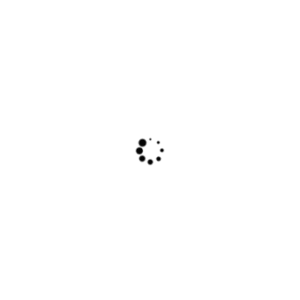
設定メニューの言語を英語にします。
設定メニューの言語を日本語にします。
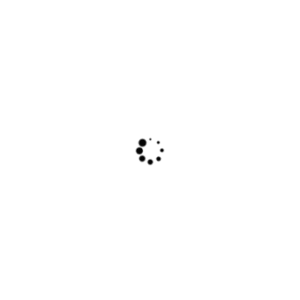
設定メニューの表示位置について、横方向の位置を調節します。
設定メニューの表示位置について、縦方向の位置を調節します。
設定メニューの透過の度合いを調節します。
操作を止めてから設定メニューが消えるまでの秒数を設定します。
[オン]のときは、状態が変化した際に情報を画面に表示します。
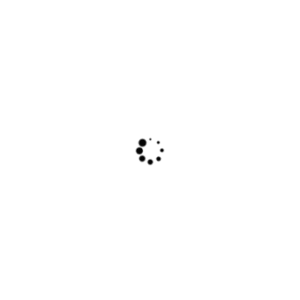
以下の項目を自動的に調整します。
水平位置、垂直位置、フェーズ、クロック
※ アナログRGB(VGA)で入力した場合だけ有効です。
画面の表示位置について、横方向の位置を調節します。
※ アナログRGB(VGA)で入力した場合だけ有効です。
画面の表示位置について、縦方向の位置を調節します。
※ アナログRGB(VGA)で入力した場合だけ有効です。
映像のノイズを軽減し、鮮明度を調節します。
※ アナログRGB(VGA)で入力した場合だけ有効です。
映像の横幅を調節します。(縦幅は調節できません)
※ アナログRGB(VGA)で入力した場合だけ有効です。
DisplayPortの対応バージョンを設定します。
DisplayPortで3840×2160 の映像を垂直周波数(リフレッシュレート)60Hz で表示したい場合、[1.2]に設定してください。
[1.1]では30Hzまでとなります。
[1.1]に戻し、ご使用のグラフィック環境の対応状況をご確認ください。
HDMI1端子のEDIDを設定します。
HDMI1で3840×2160 の映像を垂直周波数(リフレッシュレート)60Hz で表示したい場合、[2.0]に設定してください。
[1.4]では30Hzまでとなります。
[1.4]に戻し、ご使用のグラフィック環境の対応状況をご確認ください。
[オン]のときは、CEC通信機能を有効にします。
⇒ 用語解説:CEC
本製品の設定をご購入時に戻します。
※[言語]と[色設定]-[ユーザー]の設定は保持されます。
ショートカットメニューを表示するには、製品の[▲][▼]ボタンを押します。
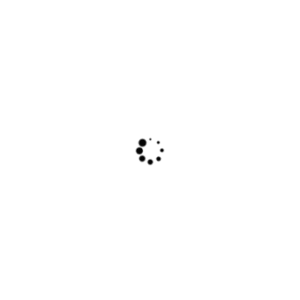
音量を調節します。
どの入力端子の音声を出力するか設定します。
画面から出るブルーライトを低減する度合いを調節します。
画面の輝度を調節します。
⇒ 用語解説:輝度
超解像機能の度合いを調節します。
⇒ 用語解説:超解像
[オン]のときは、画面右側だけに超解像処理をして映像を表示します。
超解像の効果を確認するのに便利です。
※ 子画面を表示できません。
HDMI接続機器との同期方法を変更します。
HDMI接続での画面表示に問題がある場合、設定を変更すると一部映像機器の問題が改善されることがあります。
通常は使いません。
本製品のメンテナンス時にだけ利用します。
本製品への映像入力が止まった場合の動作を設定します。
画面の表示が消えます。ランプは節電状態を示します。(省電力モード)
※ 映像入力が再開されると、自動的に画面が表示されます。
画面の表示が消えます。ランプは消灯します。
※ 映像入力が再開されると、自動的に画面が表示されます。
省電力モードに入り、一定時間が経過したら、電源をオフにします。
※ 画面を表示するには、電源ボタンを押します。
入力切換を表示するには、製品の[INPUT]ボタンを押します。
入力端子名を選ぶと、その入力だけを表示するようになります。
[AUTO]を選ぶと、映像が入力されている端子を検知し、自動的に表示する入力を切り換えます。
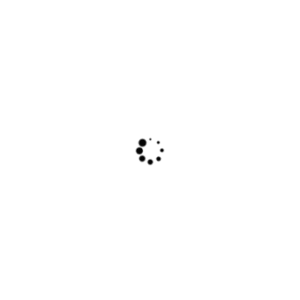
映像調整用のソフトウェアをダウンロードする
ダウンロードした「LCDTOOL.EXE」を開く
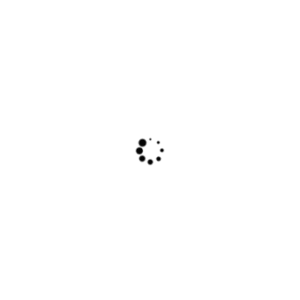
[次のモニター]をクリックして、本製品に表示します。
本製品本体の[INPUT]を3秒間押し(タッチし)続ける
⇒ 自動で映像が調整されます。
設定メニューで水平位置/垂直位置/フェーズを調節してください。
パソコンの解像度を3840×2160[アナログRGB(VGA)の場合は、2048×1152]に設定してください。
低い解像度の映像は、引き伸ばして表示されるため、アスペクト比が変わったり、画面がにじんだりする場合があります。
デスクトップを右クリック
解像度を設定できる画面を表示する
Windows 10
[ディスプレイ設定]→[ディスプレイの詳細設定]をクリック
Windows 8/7
[画面の解像度]をクリック
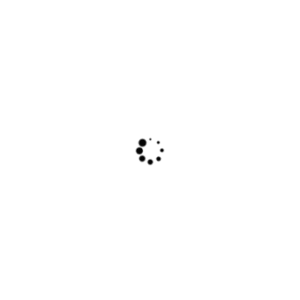
解像度を3840×2160に設定し、[適用]をクリック
※ アナログRGB(VGA)の場合は、2048×1152に設定する
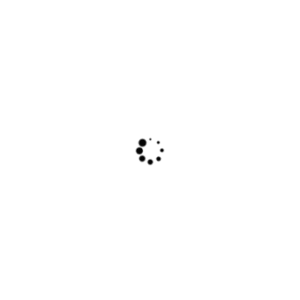
パソコンによっては、音声の出力先を設定する必要があります。
Windows の例
通知領域のスピーカーアイコンを右クリック
[再生デバイス]をクリック
本製品を選び、[規定値に設定]をクリック
macOS の例
システム環境設定の[サウンド]をクリック
[出力]タブをクリック
本製品を選ぶ
パソコンと本製品をオーディオケーブルでつないでください。
● パソコンや映像機器側の音量を確認してください
● 本製品の設定メニューの[音声設定]→[音声ソース]をご確認ください
● ヘッドホンをつないでいませんか?
ヘッドホンをつなぐと、本製品のスピーカーから音は出なくなります。
ケーブルは60Hz 表示に対応しているHDMI 1につないでください。
その後、設定メニューの[その他]→[HDMI1 EDID]を選び、[2.0]に設定してください。
設定メニューの[その他]→[DisplayPort]を選び、[1.2]に設定してください。
● 設定メニューの[映像設定]→[オーバードライブ]を[オン]に設定してみてください。
● つないだ機器が60Hz 表示に対応しているかご確認ください。
● 設定メニューの[その他]→[HDMI1 EDID]を選び、[1.4]に設定してください。
※ 設定変更することで4K 表示時は30p に制限されます。
60Hz 表示が必要なゲームなどでは残像が発生する場合があります。
● 一部の映像機器をHDMIでつないだ場合、設定メニューの[その他]→[シンク設定]を選び、[2]に設定してください。
設定メニューの[その他]→[DisplayPort]を選び、[1.1]に設定してください。
※ 設定変更することで4K 表示時は30p に制限されます。
60Hz 表示が必要なゲームなどでは残像が発生する場合があります。
「本製品」と「パソコンや映像機器」とをつなぐケーブルをつなぎなおしてください。
その際、奥までしっかりと差し込むようにしてください。
ノートパソコンの取扱説明書で「外部モニターへ出力する設定」「出力切換設定」をご確認ください。
■ Windowsの画面が表示されている場合
解像度を設定してください。
■ Windowsの画面が表示されていない場合
以下の操作をお試しください。
パソコンの電源を切る
パソコンの電源を入れ、下のような画面が表示されるまで[F8] キーを何度か押す
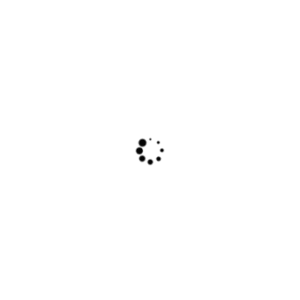
[低解像度ビデオ(640×480) を有効にする]を選ぶ
Windowsが表示されたら、解像度を設定する
本製品は高解像度のため、通常どおりの設定では文字やアイコンなどが小さく感じてしまうことがあります。
そのような場合、パソコン側の設定で画面や文字を拡大することができます。
デスクトップを右クリックし、表示されたメニューの[ディスプレイ設定]をクリック
複数のディスプレイがある場合、本製品に合うディスプレイを選ぶ
「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」でスライダーを動かし、大きさを設定する
[ディスプレイの詳細設定]→[テキストやその他の項目のサイズ調整]の順にクリックします。
画面全体を拡大するのではなく、タイトルバーやメニューの文字だけを拡大します。
画面を大きく使うことができますが、ボタンやアイコンのサイズは拡大されません。
[適用する]をクリック
Windowsからサインオフする
デスクトップモードにする
画面左下を右クリックし、表示されたメニューの[コントロールパネル]をクリック
[デスクトップのカスタマイズ]をクリック
[テキストやその他の項目の大きさの変更]をクリック
複数のディスプレイがある場合、設定画面を本製品上に移動する
「すべての項目のサイズを変更する」でスライダーを動かし、大きさを設定する
画面全体を拡大するのではなく、タイトルバーやメニューの文字だけを拡大します。
画面を大きく使うことができますが、ボタンやアイコンのサイズは拡大されません。
[適用]をクリック
Windowsを再起動する
複数ディスプレイをお使いの場合、本製品の画面や文字だけを拡大することはできません。
[スタート]→[コントロールパネル]をクリック
[デスクトップのカスタマイズ]をクリック
[テキストやその他の項目の大きさの変更]をクリック
拡大するサイズを選び、[適用]をクリック
画面右側の[カスタム テキスト サイズの設定(DPI)]をクリックし、マウスでルーラー(定規部分)をドラッグします。
⇒ ドラッグに応じて、サイズが変化します。
変更したいサイズになったら、[OK]をクリックし、新たに表示された[カスタム]を選んで[適用]をクリックしてください。
※ 設定によっては、一部項目が画面から飛び出したり、項目が崩れたりすることがあります。
[今すぐログオフ]をクリック
画面全体を拡大するのではなく、タイトルバーやメニューの文字などを拡大します。
画面を大きく使うことができますが、ソフトウェアのボタンなどは拡大されないことがあります。
① デスクトップを右クリックし、表示されたメニューの[個人設定]をクリック
②[ウィンドウの色]をクリック
③[デザインの詳細設定]をクリック
④ 各項目のフォントサイズを選びます。
⑤ すべて設定が終わったら、[OK]をクリック
⑥「ウィンドウの色とデザイン」画面が表示されたら、[変更の保存]をクリック
本製品はご購入時の設定では、選択中の入力端子から映像が入力されていないときに、映像が入力されている端子を検知して自動的に入力を切り換えます。
選んだ入力端子以外に自動で切り換わるのを避けたい場合は、以下のように操作します。
本製品の[INPUT]ボタンを押し、表示したい入力端子を選びます。
これで、選んだ入力端子以外を自動的に表示することはなくなります。
本製品はご購入時の設定では、選択中の入力端子から映像が入力されていないときに、他の映像が入力されている端子を検知して自動的に入力を切り換えます。
この機能が停止してしまって戻したい場合は、以下のように操作します。
本製品の[INPUT]ボタンを押し、表示したい入力端子を選んだ。
この操作をすると、[AUTO]状態が解除され、選んだ入力端子以外を自動的に表示することはなくなります。
本製品の[INPUT]ボタンを押し、[AUTO]を選びます。
これで、[AUTO]状態になり、選んだ入力端子から映像が入力されていないときに、映像が入力されている端子を検知して自動的に入力を切り換えるようになります。
本マニュアルをお手元でご覧になるための方法をご案内します。
 全ページプリント(PCのみ)
全ページプリント(PCのみ)上のボタンをクリックすると、本マニュアル全体をWebブラウザーのプリント機能で印刷できます。
ただし項目が多いマニュアルはページ数が多くなり、全体の印刷には向きません。
プリントしたいページを開き、そのページだけをWebブラウザーのプリント機能で印刷することをおすすめします。
※ マニュアルの内容量によっては、印刷が始まるまで数分掛かることがあります。
※[全ページプリント]ボタンは、スマホ・タブレットではお使いになれません。
本マニュアルで使用しているソフトウェアライセンス情報やGoogle アナリティクス4の利用については、こちらをご覧ください。
このページはお役に立ちましたか?
 映像の階調をコントラストが上昇するように調節しながら、RGB(赤・緑・青)にCMY(シアン・マゼンタ・黄)を加えた6色の座標軸で色の補正をする機能。
映像の階調をコントラストが上昇するように調節しながら、RGB(赤・緑・青)にCMY(シアン・マゼンタ・黄)を加えた6色の座標軸で色の補正をする機能。