 |
|
USBハブを使用してツリー状接続ができます。ツリー状接続とは、木の枝のように先端(上)に進むにつれて分岐していく状態を例えたもので、元をたどれば1本になる、つまり1台のパソコンに辿り着くといった状態です。
USBハブはLAN製品のハブに似たような製品ですが、LANの場合複数台のパソコンを接続可能なのに対して、USBハブの場合はパソコンを1台だけ接続できる点が大きな違いです。
|
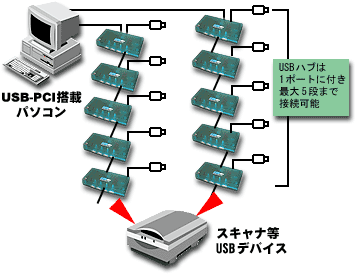 |
USBデバイス及びUSBハブはUSBケーブルで接続します。ケーブル1本の最大長は5mで、ツリー状接続でUSBハブが最大5段までなのでもっとも遠いデバイスは30mとなります。また、USBケーブルの両端には形状の異なるコネクタが採用されています。一方を「シリーズAプラグ」もう一方を「シリーズBプラグ」と呼び、それぞれツリー状接続で(ルートハブも含む)上流用(アップストリーム)と下流用(ダウンストリーム)として使い分ける必要があります。
 |
 |
| 「Aプラグ(長方形)」 |
「Bプラグ(正方形)」 |
アップストリーム、ダウンストリームってなに?
上流(アップストリーム)・下流(ダウンストリーム)とはUSBデバイスまたはUSBハブからパソコン側(USBインターフェイス側)を見たときに、パソコン側が上流となります。下流のUSBデバイスには必ず「シリーズBプラグ」用のコネクタ(Bポート)が搭載されています。コネクタ形状の違いは逆差し防止が主な目的で、ピン数はどちらも4ピンです。 |
|
|
 |
|
USBはデバイスを繋げれば自動的に認識されドライバがインストールされる仕組みになっています。
例えばUSB接続のプリンタを初めて接続した場合、Windows98がドライバを要求してくるのでCD-ROMやフロッピーディスクからドライバをインストールします。これでプリンタは使用可能となるのです。
一度インストールすれば、その後はドライバは要求されません。最初の1回だけドライバをインストールすればその後は抜き挿し自由なのです。
|
 |
|
パソコンの電源ONの状態でデバイスの抜き挿しが可能であることを指す表現です。デバイスの抜き挿しの際にパソコンの電源を切ったり、再起動したりする必要はありません。使用したいUSBデバイスを使用したいときにだけ自由に抜き挿しできる大変便利な機能です。
|
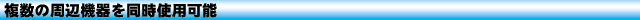 |
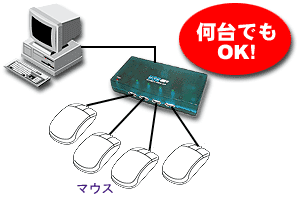 |
USBの仕様上最大127台のUSBデバイス(USBハブを含む)が接続できることになっていることは前項でも触れましたが、USBデバイスの同時使用も可能です。
例えばUSBマウスを2つ以上接続した場合、どちらのマウスを動かしてもマウスポインタは反応して動きます。またUSBキーボードも同じで、2つ接続すればどちらからも入力可能です。
USB接続のフロッピーディスクドライブやスピーカー、プリンタ、ジョイスティック等は複数台を同時使用できます。
|
|
| USBインターフェイス
| USBの特徴 その2へ→ |

