


![[提案ひな型付 ]命名くんの導入、提案書をダウンロードして簡単提案](/biz/sp/dencho/column/images/pic04_01.jpg)
本企画は、電子帳簿保存法(以下「データ保存法」といいます。)の改正に対して、最小限で平易に対応することを目標としています。
データ保存法は、突き詰めれば紙を経理業務から根絶することも可能です。
ただ、そこに向かうにしても、まずは最小限の労力で組み込みソフトランディングさせたいと考える現場担当者、マネージャー、取締役から話を聞きます。
そのまま使える提案書のひな型もダウンロードできます。
それぞれの立場を理解した上で、提案書を作ってみますので使ってください。

個人事業主であれば、導入するかどうかの判断は早いかもしれません。
一方、中小企業であれば、人事評価を使って導入をなめらかにしましょう。
現場の聞き取りをしていると、データ保存法への対応が難しいと感じる人が多いです。
その理由は、複数の領域にまたがって分かりにくいから。
結果、どの機器やソフトウェアを使って、全体の業務フローを改善することを考え出すと、途端に難易度が上がるのです。
また、最低限の対応をする場合に、過不足なしに対応させるのは神経を使います。
以下、導入を促進させるため、人事評価の観点から、担当者別にお伝えしたいことをまとめます。
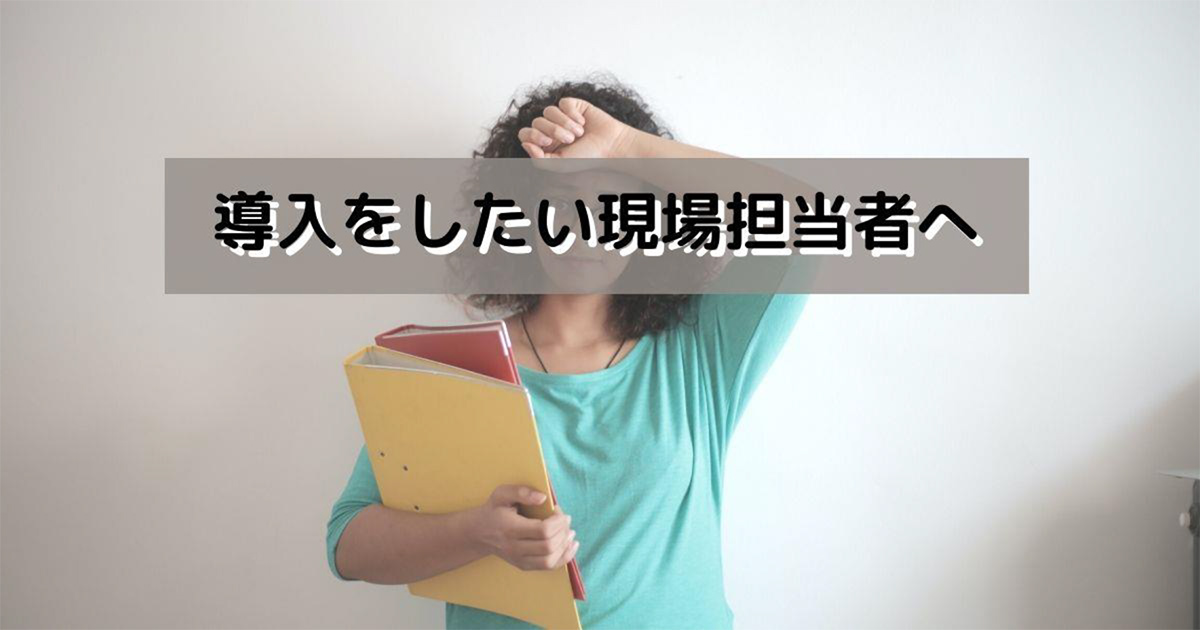
日頃の業務が多いのに、「改正があったから対応してね」なんて軽く言われませんか?
おそらく、役員やマネージャークラスの多くの方は、データ保存法の改正の対応が難しいことをあまり理解していません。
だからこそ、現場が今から取り組む、難しさがあることをはっきり伝える、現場に影響がないようゆっくり導入を進めるようにします。
そして、法改正の対応をしたことを、必ず人事評価でアピールしてほしいです。
バックオフィスの方が、人事考課でアピールする点があまりないということを耳にします。
「間違わなくて当然」「できて当たり前」のような評価をされることが多い部門だから。
バックオフィス系の方からは、営業関係の方と異なり目標設定が難しいことを聞きます。
でも、2022年7月~2023年12月までの1年半あれば、必ず目標としてアピールできる機会が出ます。
そして、この改正法への対応は、取り組んだ点のアピールとして適度な難易度を持っています。
早めに導入や提案だけでなく人事評価をされることを見越して、自身に過度な不可がかからない状態を維持しつつ、取り組んでください。
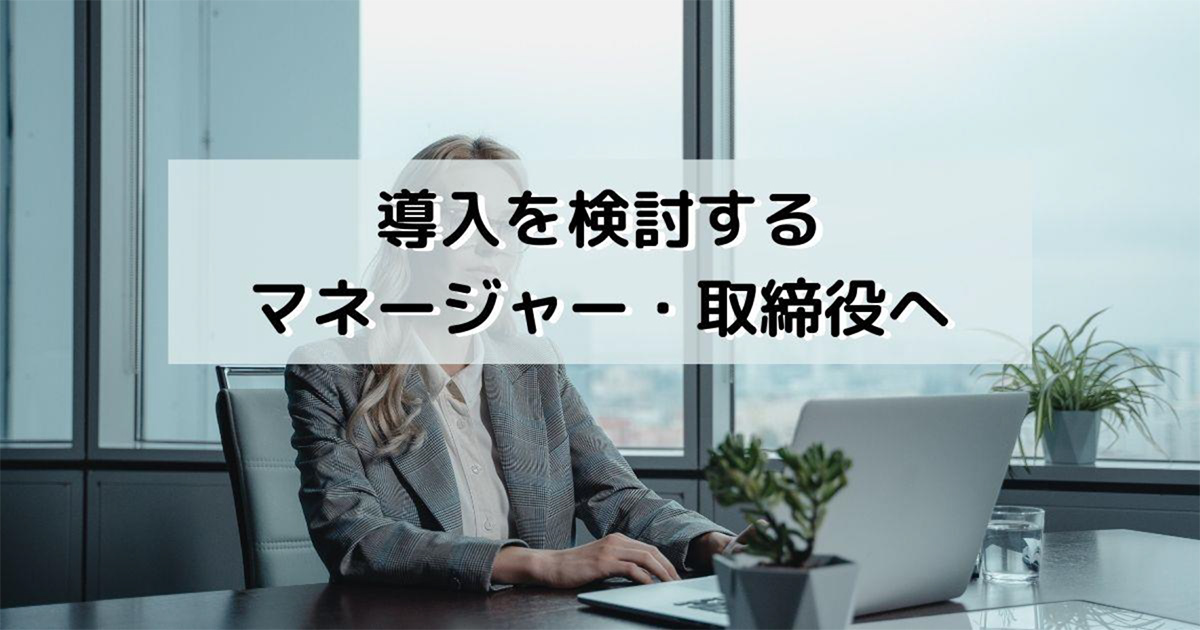
データ保存法の改正は、領域にまたがった仕事です。
現場の方だけでなく、マネージャークラス以上の方は、調整の手腕を見せられるいい課題にできます。
マネージャーといっても、昨今は名ばかりだったり、現場や最上級の方へ権限が移譲されていたり、うまくポテンシャルを発揮できない場面があるかもしれません。
また、取締役といっても現場からの距離があって、対応しにくいかもしれません。
データ保存法は、現場対応に近いにも関わらず調整箇所が多く出てくるので、経理関係の話だけにおさまらず、営業担当者や役員の方にもお願いすることが出てくるでしょう。
保存機械を購入することも考えれば、その対象は多岐にわたります。
現場担当者は仕事を多く抱えて、積極的に動きたくない場合もあります。
だからこそ、いい潤滑剤としての役割、マネージャー以上の方の力を示すいい課題です。
早期に取り組めば、それほど負担はありません。
なお、マネージャー以上の立場から促進させるときに、部下に、ちゃんと評価を与えるよう意識します。
間違わないことが当然と思われている部署に、新しいことを導入させるには、ごほうびがあるといいので。
繰り返しになりますが、データ保存法への対応は、普段の仕事のように「やって当然」ではなく、けっこう面倒な点が多いです。
評価を促進剤として使っていきましょう。
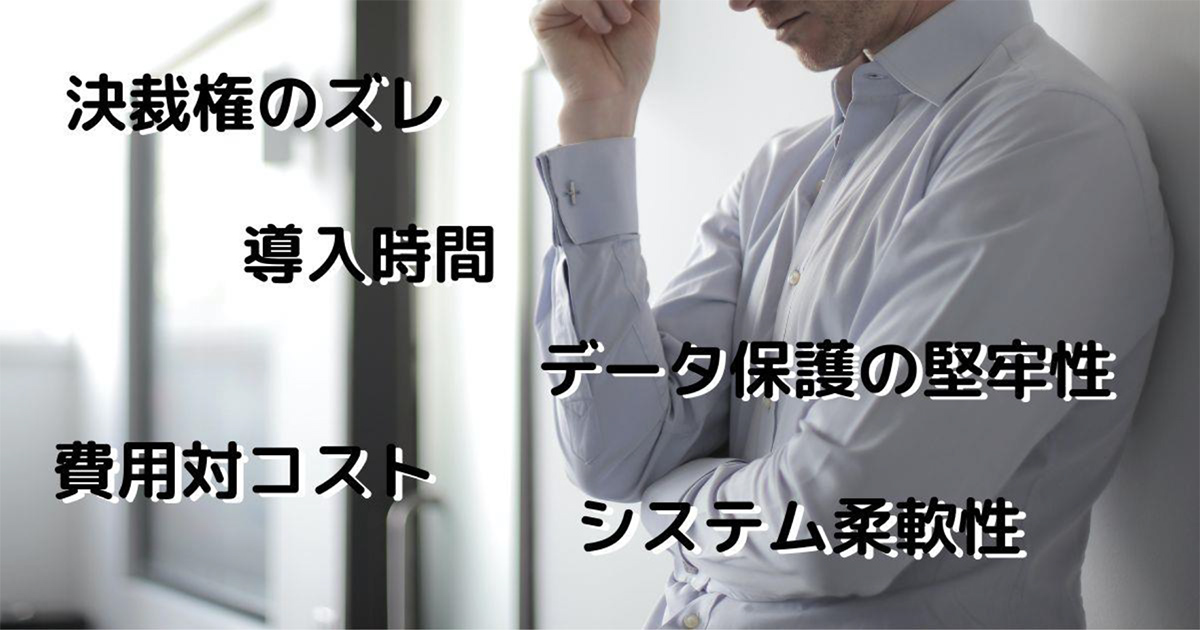
人事評価をしてもらう、人事評価をする立場として、データ保存法の課題をおさらいしておきましょう。
ソフトウェアや機器、処理フローを決められる決裁権のある人と、現場の人が分かれていることから、導入対応には話し合いや調整が必要です。
個人事業主には課題点となりませんが、大小を問わず組織であればこの調整は大変です。
経理系は、ずっと動いている部署です。
高速道路を改修するのと同様に、運営へのマンパワーを改修へ割かないといけないため、なかなか大変です。
また、決裁権のある人と現場の人のやり取りが発生します。
意外とこのやり取りを好まない現場の方も見かけます。
調整するというのは、意外と難しい話なのです。
機器を決めて、ソフトウェアを決めて、購入したら即導入になるのでしょうか?
そうはなりません。
データ保存法のデータ保存義務でPDFなどを保存すれば、紙の書類は破棄していいです。
でもちゃんと動いている確証を得てからでないと、破棄は社内から反対を受けることが多いです。
紙とデータ保存とを2ヶ月程度は併用して、困らないことが分かってからでないと、社内の慎重派の方は、導入に納得しないでしょう。
併用して走らせるとしたら、2024年1月よりもっと前、余裕を持って対応しないと間に合いません。
なお、保存義務はすでに発生していますが免除されている状態。
2022年1月から、原則的に、データでの保存義務は発生しているのです。
データ保存法の改正に対応するコストがうまく見積もれないという話を聞きます。
最近セミナーに参加しても、どういう法改正があるか、データ保存法の歴史とはなにかから話してくれます。
でも、最終的に現場の方が知りたいのは、対応にどれくらいの費用がかかるかです。
本稿が扱うもので、実質のコストはBRD-UT16Dの27,090円[税別]です。
 早く対応すれば、5年分のブルーレイディスク5枚(執筆時に調べると3,794円[税別])が特典でついてきます。
早く対応すれば、5年分のブルーレイディスク5枚(執筆時に調べると3,794円[税別])が特典でついてきます。
一方で、コスト比較で出るべきは、紛失した場合の、領収書をデータで取引先に再発行する労務コストや、税務調査でデータを税務調査官に持っていかれるリスクです。
自然発生する後者のコストを対比としておくといいです。
他と組み合わせができるシステムかどうかをよく検討しましょう。
本稿でオススメしているのは、保存機器とそれに伴って1年間無償利用ができる命名くんのソフトウェアです。
一方、精算システムなどと合わせて、今回のデータ保存法への対応を考えることもできます。
でも、データ保存のためだけにシステムをガツッと入れられるかといえば、かなり判断しにくいでしょう。
精算システム本体に興味があれば別ですが、保存するだけ、最低限の対応だけを考えるなら、本稿のような安いシステムを社内提案したいものです。
パソコンのデータはよく消えます。
自分のパソコンのデータだけでよければ、なんとなくの寿命が分かるかもしれません。
でも、組織で使っていれば、その勘所が働かない。
気づいたらデータが消えるという懸念があります。
データが消えたとき、取引先に領収書を依頼しなければならないという嫌な仕事が経理の方に発生するとすれば、費用対効果以上に、現場の人は安心できる保存機器を求めるでしょう。
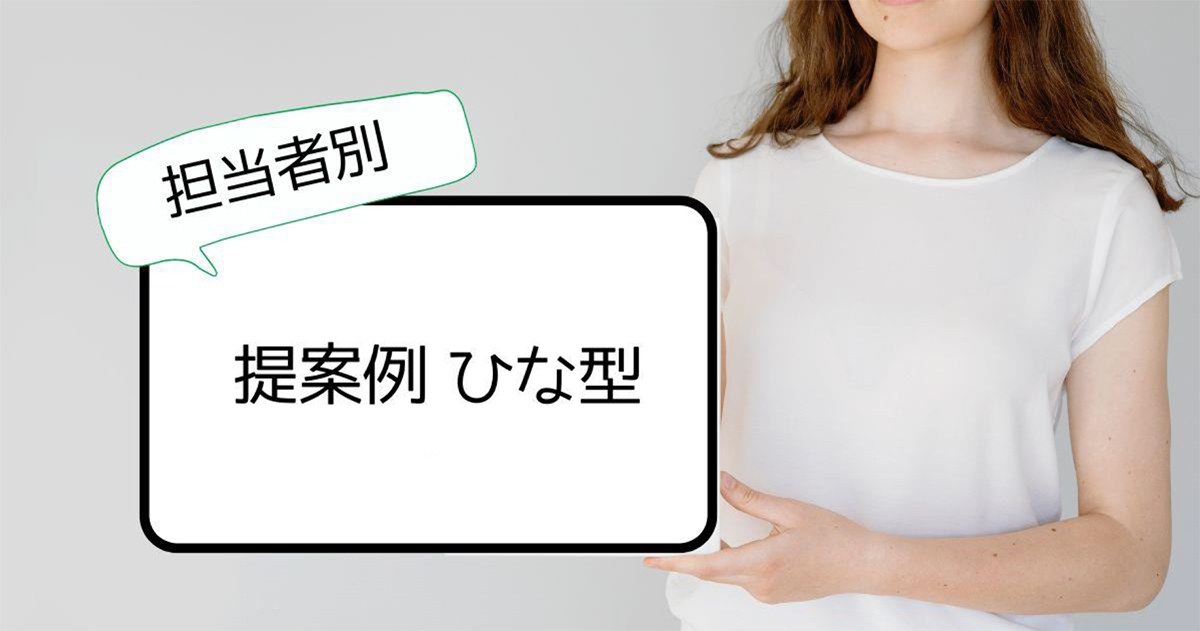
個人事業主・中小企業の現場担当者・中小企業のマネージャー以上の方が提案する上で、ひな型を作成しました。
データ保存法について、考える情報収集をする よりも、動く 少しずつ制度構築を進める方が、早く結果が出ます。
ぜひ、ダウンロードして使ってください。
個人事業主の方に向けては、損していないかという自分への理解が必要です。
その意味での提案書を作ってみました。
ダウンロードして納得してみましょう。
中小企業で現場が提案する場合には、社内提案が必要でしょう。
これまでの論点をまとめた提案書を用意しました。
ダウンロードして、必要な箇所をコピペして利用しましょう。
役員やマネージャーが提案する場合には、現場にちゃんと説明ができる資料がほしいです。
役員・マネージャーが上滑りしないように、地に足をついて現場の人と並走したいです。
こちらの資料をダウンロードしてお役立てください。
最低限の対応をすることを目的にまとめている本稿ですが、最後にこの言葉をお伝えします。
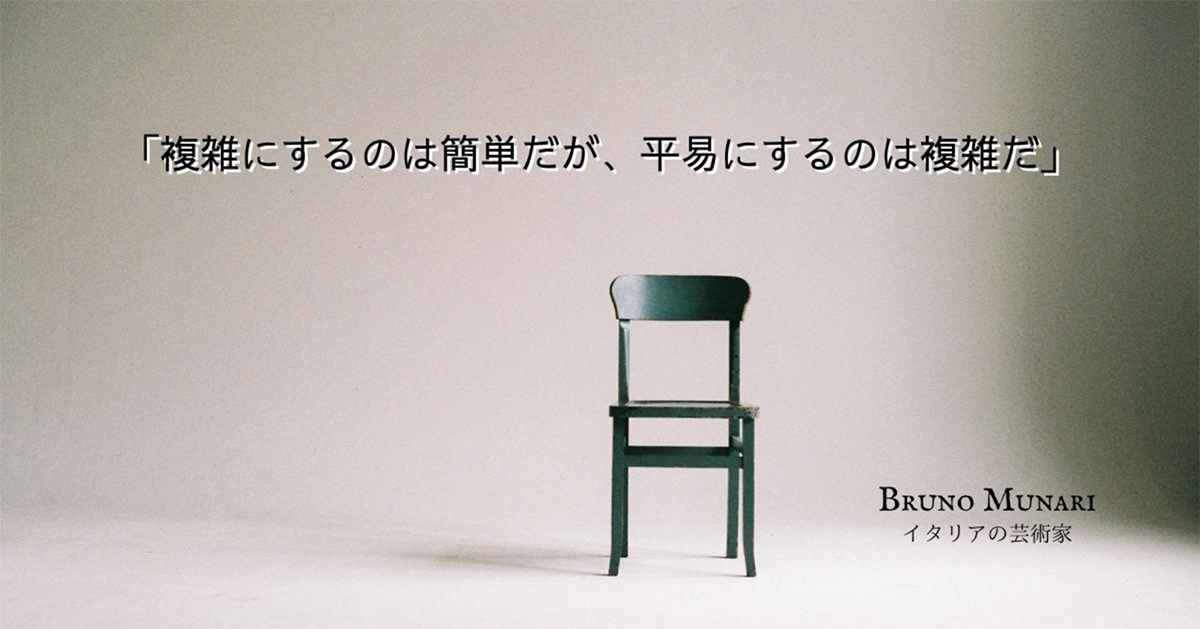
みなさんは、平易(最低限)に取り組むことを目指しています。
難しいことをしているという自信を持って取り組んでみてください。