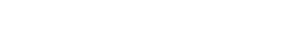らくらくボード「IWB-651EB」導入事例
【奈良県 橿原市立白橿北小学校】
導入事例TOPへ戻る
取材日:2021年7月2日

橿原市立白橿北小学校は、大和三山の1つとして知られる畝傍山をはじめ、金剛山、葛城山などを臨む、自然豊かな白橿町に立地する公立小学校です。全校7クラスと特別支援学級から成るアットホームな雰囲気の中で、「たくましいかしのみっ子」の育成に努めています。
全クラスへの電子黒板の導入が進みつつある同校で、先行して「らくらくボード」を活用してきたのが笹岡智佳子先生(2年生担任)です。今回、算数の授業を見学させていただき、「らくらくボード」の導入効果などについてお話を伺いました。
電子黒板、タブレット、クラウドツール……、これからの教室のICTとは

 授業の冒頭では、「らくらくボード」に練習問題を表示して、復習の時間を取っていましたね。チーム対抗のクイズ形式だったせいか、児童の皆さんも大変な盛り上がりでした。
授業の冒頭では、「らくらくボード」に練習問題を表示して、復習の時間を取っていましたね。チーム対抗のクイズ形式だったせいか、児童の皆さんも大変な盛り上がりでした。
笹岡先生いつも元気よく、一生懸命取り組んでくれる子どもたちですが、電子黒板が導入されてからはより積極的になったと思います。授業の最初の数分間でこのようなミニドリルを行うのには、「つかみ」の意味もあり、また、前回の授業内容の定着を図る目的もあります。1人1台ずつChromebookを導入済みですので、それぞれ黙々と取り組ませることもできるのですが、やはり最初は皆で電子黒板に向かって一体になることを重視しています。
 その後、Chromebookを使って問題を解いていましたが、教材はどのようなものを使われていますか。
その後、Chromebookを使って問題を解いていましたが、教材はどのようなものを使われていますか。
笹岡先生タブレット学習ソフトの「ミライシード」、協働学習用にGoogle Jamboard、またNHK for SchoolやYouTubeなどのコンテンツでも、 よいと思えるものはどんどん活用しています。授業支援ソフト「ロイロノート・スクール」は、WebカードでURLを安全に共有できますので、調べ学習によく使います。ミニドリルはフリーで配布されているものですね。このような様々な教材を組み合わせて、学習の定着や意欲の持続につなげています。
 この環境で電子黒板はどのような役割を担っていますか。
この環境で電子黒板はどのような役割を担っていますか。
笹岡先生まずはクラス全員での画面共有です。子どもたちがChromebookで行った作業の成果を、大画面で一緒に見ることが大切です。自分の解答を皆に見てもらい、それについて説明することが考える機会につながります。とはいえ、こうすることでほかの人の画面、つまり解答が見えてしまうことになりますので、当初は試みとして「あり」なのかどうかと躊躇もしました。しかし実際には、「できた子」が「まだできていない子」に気付いて自主的に教えてあげたり、友だちの解答に関心を持って質問したりということが自然に発生するなど、非常によい効果が生まれています。
浦西教頭「間違えることはいけないこと」という思い込みのある子どもは、共有という手段を、とりあえず正解を手に入れるために使いがちです。対してこのクラスの子どもたちは間違えても恥ずかしがらず、「何がいけなかったんだろう」と考えることができています。友だちの「わからない」から興味を持って、皆が一緒に考えられるようになりました。
 電子黒板で考えを共有することに慣れていくうちに、「間違えても恥ずかしくない」という安心感が生まれたのでしょうか。
電子黒板で考えを共有することに慣れていくうちに、「間違えても恥ずかしくない」という安心感が生まれたのでしょうか。

笹岡先生その通りだと思います。「わからない」と言えることはとても大事なこと。それを伝える練習もして、恥ずかしい思いをしないような雰囲気作りも心がけています。さらに、1つの解答に対して自然と別の意見が出てくる、このような対話が生まれる直接のきっかけは、やはり共有ですね。まさに対話的な学びが実現していると感じます。
低学年では、注目させたい場面で集中的に活用

 「らくらくボード」やChromebookと、既存の黒板やノートの使い分けで意識していることはありますか。
「らくらくボード」やChromebookと、既存の黒板やノートの使い分けで意識していることはありますか。
浦西教頭 笹岡先生の授業では、ツールの利用頻度など、バランスが非常によく考えられていると思います。今回の授業では、液体の体積を測って実演していましたが、例えばこれは、あらかじめ撮影された映像を使って、オールデジタルで見せることも可能でしょう。
ですが、笹岡先生はあえて具体物をWebカメラで撮影して、「らくらくボード」の画面に拡大表示しながら説明していました。いくらデジタル化が進んでも、具体物で学ぶということも同時に大切にしていかなければなりません。
例えば、1リットルのペットボトルを自分の手で持ったことがあれば、その重みを筋肉が覚えています。このような実感を忘れないようにしながら、電子黒板でよりわかりやすく補っていくという、この配分が絶妙だと思います。

笹岡先生電子黒板の活用にはたしかに工夫が必要で、学年に合わせた使い分けも求められます。小学校低学年ではメリハリをつけて、注目させたい場面で集中的に使うのがよいですね。少なくとも1日1回は、必ず電子黒板をどこかで使うようにしています。黒板やノート、Chromebookなどを、どんな配分で組み合わせるかが考えどころです。
浦西教頭学びを定着させるためには、板書をノートに写すことが重要だと考える先生は少なくないのですが、それは思い込みかもしれません。板書に時間をかけるなら、その分問題をたくさん解いたほうがよいという場面も間違いなくあります。ノートを取らずに、教科書に直接書き込んだっていいのです。電子黒板のような新しいツールが導入されることは、教員にとって学びのあり方を見直すきっかけにもなっています。

笹岡先生特に板書についての柔軟な取り組みは、デジタル教科書を表示させて、そこにいくらでも書き込みできる電子黒板があってこそ。以前は子どものノートを写真に撮って、HDMI経由で大型ディスプレイに表示するといったことも行いましたが、かなりの手間がかかっていました。今ではChromebookと「らくらくボード」を使って、一瞬で全員の画面を共有できます。サポートが必要な児童がいれば一目でわかりますし、時間もより有効に使えています。
個別最適化の学びを実現させるために

 授業中、児童の皆さんから「もっと問題を解きたい」「もっと勉強したい」という声が挙がっていて、高い意欲が伝わりました。
授業中、児童の皆さんから「もっと問題を解きたい」「もっと勉強したい」という声が挙がっていて、高い意欲が伝わりました。
「らくらくボード」の効果について、実感されていることがあったら教えてください。
浦西教頭電子黒板は、視覚と聴覚の両方から情報が入ってくるので、どちらかを苦手とする子どもたちにとっても有難いものです。例えば、教科書のどこを見ればいいのか、言葉で説明されるだけではわからないという児童もいます。そんな時、電子黒板の画面に教科書が表示されていれば、「ここだ」とすぐにわかるわけです。私はこれまで特別支援学級を指導してきた経験がありまして、多様な子どもたちの学習支援については常に注目していますが、電子黒板はその一助になるでしょうね。
笹岡先生例えば高学年になれば、低学年からの積み重ねがうまくできていないという児童も出てきます。そんな場合には、無理してほかの児童と同じことをせず、ミライシードなどを使って、自分のレベルに合った問題に取り組んでいてもいいんです。前に戻って、わからないところから納得いくまでやり直してもいい。授業のICT化が進むことで、様々な障壁が取り払われ、それぞれに合った指導ができるようになってきていますね。

浦西教頭デジタル教材がさらに増えることで、学びの手段はさらに多様化していくでしょう。「できる子」にはもっと自信をつけてあげて、支援が必要な子にはスモールステップで教えていく──、教室でもこのような個別最適化の学びが実現するはずです。先生方はそこに到達するために、学びの本質は何かという部分を突き詰め、踏み出していく必要がありますが、それを適切にサポートしてくれることを「らくらくボード」などのICT機器に期待しています。
導入学校概要

- 学校
- 橿原市立白橿北小学校
- 所在地
- 奈良県橿原市
- 開校
- 昭和52年
- ご協力いただいた
先生 - 橿原市立白橿北小学校 笹岡智佳子先生
橿原市立白橿北小学校 浦西礼美教頭
※ミライシードは株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。
※ロイロノートは株式会社LoiLoの登録商標です。


 商品一覧
商品一覧