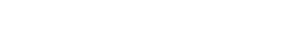Q&A
パソコンからNAS(ネットワーク型ハードディスク)を使う場合に気をつけること【基本編】
NAS(ネットワーク型ハードディスク)を使う場合に注意しておきたいこと、USBハードディスクとは使い勝手が異なるNASならではの動きを集めてみました。NASを初めて使う時の参考にしてください。
なお、ここでは一般的なNASの動作について解説しているため、製品によって例外が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
<目次>
削除したファイルはパソコンのゴミ箱に入らない
ドラッグ&ドロップした場合は移動ではなくコピー
フォルダーと共有フォルダーの違い
日頃のバックアップの重要性
NASは小さなパソコン
強制シャットダウンは厳禁!
同時アクセスに要注意
NASは複数ユーザーで使うもの?
NASのデータ復旧は非常に高額
NASもパソコンもセキュリティ対策が大事
NASでできること
NASがインターネットにつながるメリット削除したファイルはパソコンのゴミ箱に入らない
NASのファイルやフォルダーを削除した場合、パソコンのゴミ箱には入らずにそのまま削除されます。1つの操作ミスで取り返しのつかないことにならないよう、ファイルの取り扱いには十分に注意してください。
なお、NASによってはNAS上に用意されたゴミ箱に入る場合もあります。(追加設定が必要な場合もあります。)ドラッグ&ドロップした場合は移動ではなくコピー
パソコンのファイルやフォルダーをNASにドラッグ&ドロップした場合は「コピー」となりパソコンにはファイルやフォルダーが残ります。(パソコン上で同じ操作を行った場合は移動になります。)
パソコンのファイルやフォルダーを「切り取り」してNASに「貼り付け」した場合は、パソコンにファイルやフォルダーは残りません。フォルダーと共有フォルダーの違い
NASには共有フォルダーとフォルダーという2つのフォルダーがあります。
パソコンで普段使っているフォルダーは「フォルダー」で、NAS専用のフォルダーが「共有フォルダー」となります。
共有フォルダーは、特定のユーザーのみがアクセスできるようにアクセス制限を掛けたりすることできる、特別な役割を持ったフォルダーです。
共有フォルダーは誰でも作成できる訳ではなく、NASの管理者のみが作成でき、作成できる数には上限があるケースが多いです。日頃のバックアップの重要性
NASにデータを大切なデータを保存した場合は、NASのデータの定期的なバックアップを行ってください。
「定期的に行う」ことがポイントで、一度バックアップを行っても、それから時間が経ってからNASが故障してしまうと、バックアップしてから故障するまでに保存したデータが失われてしまいます。
NAS等のストレージ製品は劣化により故障してしまうため、USBハードディスク等の他の製品にバックアップ(二重化)しておくと、もしもの時に安心です。NASは小さなパソコン
NASは、中にWindowsのようなシステム(OS)が入っている小さなコンピューターです。
パソコンと同じように、NASの電源を入れた後にNASの中のシステムが起動するまでに数分掛かります。同様に電源を切る時も、数十秒から数分かかります。
USBハードディスクの電源を入れるとすぐに起動して認識できるのは、内部にシステム(OS)を持たないためです。強制シャットダウンは厳禁!
1つ上で述べたように、NASは内部にシステムを持っています。
パソコンは、正しい方法で電源を切らないと作業中のファイルが破損したり、最悪の場合ハードディスクやシステムが破損して起動ができなくなります。
NASもパソコンと同様に、正しい方法で電源を切らなかった場合(強制シャットダウン)、同様に製品の故障やシステム起動異常が発生することがあります。
NASのマニュアルを確認して、正しい方法で電源を切りましょう。同時アクセスに要注意
NASはネットワーク上のパソコンから同時にアクセスできる便利な製品ですが、同時アクセスできるからこそ注意しなくてはいけない点もあります。
例えば、NASにユーザーAが保存した後にユーザーBが同じファイル名で保存した場合、先保存したユーザーAのデータがユーザーBのデータに上書きされてしまい、ユーザーAのデータがなかったことにされてしまいます。
Excelなどアプリによってはユーザーがファイルを開いている場合、開いているユーザー以外は読み取り専用になり編集できなくなるといった配慮がなされていますが、そうならならいアプリもあります。
複数人で同じファイルを扱う場合は、簡単なルールを決めておくとトラブルを防ぐことができるかもしれません。NASは複数ユーザーで使うもの?
NASというと複数のユーザーでファイルの共有を目的として使用するイメージがありますが、実は個人で使う場合でも非常におすすめです。
例えば、個人がパソコンとスマホとタブレット等、複数の端末を所有している場合、パソコンからNASに保存した写真や動画をスマホやタブレットから見るといったことも可能です。
例のような使い方はクラウドサービスでも実現できますが、一定の使用容量を超えると月額の料金が発生する場合がほとんどです。その点、NASの場合は買い切りになるため、追加費用が掛からない点がメリットになります。NASのデータ復旧は非常に高額
NASが故障した場合や、誤ってデータを削除したり上書きした場合は、メーカーやデータ復旧専門のサービス会社等でデータ復旧を試みることができます。
データ復旧に成功すれば、希望するデータの全て、または一部分が戻ってきます。
ただし、NASのデータ復旧には非常に高度な技術が要求されるため、一般的にはUSBハードディスクのデータ復旧と比較して非常に高額となります。(費用が100万円以上になるケースも珍しくありません。)
日頃からバックアップを行い、データ復旧に頼らない運用をしておくことが重要です。
そもそもデータ復旧に成功する保障はどこにもないため、「データ復旧できるからバックアップしない」という考え方は成り立ちません。NASもパソコンもセキュリティ対策が大事
NASは同じネットワーク上のパソコンやスマートフォンから簡単に接続することができます。
裏を返せば、セキュリティ対策をしっかり行っていないと、誰でもNASのファイルにアクセスできてしまうので、ネットワークに簡単に参加されないように注意が必要です(特にWi-Fiルーターのパスワード漏洩)。
NASの多くは共有フォルダーに対してアクセス制限を掛けることができるため、これらの機能を使ってセキュリティ対策もしっかり行っておきます。
また、パソコンがウイルスに感染してしまった場合、ウイルス感染したファイルがNASに保存され、そのファイルにアクセスしたパソコンがさらに感染…という、ネットワークのどこからでもアクセスできるというNASの特性が感染を広げる要因になってしまうケースもあります。
ネットワーク上のパソコンもセキュリティソフトをインストールする等、ウイルス対策が必要です。NASでできること
NASは内部にシステムを持っているため、製品によって色々と便利な使い方ができます。
一般的には高額なNASほど、ハードディスクの容量が大きくなり、搭載されている機能も多くなる傾向があります。
ここではNASでどんなことができるのか、一例をご紹介します。- 共有フォルダーへのアクセス制限
- スケジュールによる自動起動・自動シャットダウン
- USBハードディスクへの定期的な自動バックアップ
- 複数のハードディスクを使用したデータ保護(RAID)
- 離れた場所からデータにアクセス★
- スマホで撮影した写真や動画の保存
- クラウドサービス(DropboxやOneDrive、GoogleDriveなど)と連携したデータの自動同期★
- 異常発生時にメールでお知らせ★
- テレビ番組の録画や再生
- 時刻の同期(補正)★
- セキュリティ対策(ウィルス対策)★
- システム(ファームウェア)の自動アップデート★
NASがインターネットにつながるメリット
NASは、NASがつながっているルーター経由でインターネットに接続することができます。
NASがインターネットに接続することで、インターネットを使った特定の機能を使えるというメリットがあります。(1つ上の★がついた機能はインターネット接続が必要です。)
これらの機能を使わない場合、インターネット接続は必須ではありませんが、一般的には接続することが推奨されています。
| Q&A番号 | 32493 |
|---|---|
| このQ&Aの対象製品 |
このページのQRコードです。
スマホのカメラで読み取ることで、スマホでFAQを見ながらパソコンの操作ができます。


 商品一覧
商品一覧