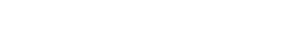- 2006年 カートリッジスタイルという発想
- 2002年 ハイビジョンレコーダーの新しいカタチ
- 2002年 販売台数業界トップを独走 新規格対応力に高い評価
- 2001年 画質とデザインへのこだわり
- 1995年 メモリーのアイ・オーから総合周辺機器のアイ・オーへ
- 1991年 もっと大きい画面が欲しい よりリアルに高速描画したい
- 1987年 印字の美しい画期的なFAX
- 1984年 IOバンク方式で業界標準を宣言 快適メモリー環境が時代を変えた
- 1983年 ストレージ製品への足がかり
- 1980年 すし屋で安心会計「マイコン寿司」システムの開発
- 1980年 ホビー機を実用マシンに変身
- 1979年 熟練の職人技をコンピュータ化 先端技術のイメージスキャナーも自作
- 1976年 コンピューター黎明期に創業 データの入出力関連に特化したい
HOME > 会社案内 > 会社情報 > 会社の歴史 > 1995年 メモリーのアイ・オーから総合周辺機器のアイ・オーへ
1995年 メモリーのアイ・オーから総合周辺機器のアイ・オーへ
【外付けハードディスク】開発:1995年
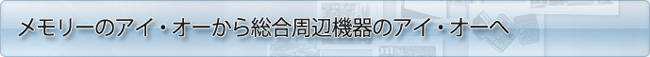
リスクをチャンスに変えて
 時は1995年。年末にWindows95の発売が予定されていた。
時は1995年。年末にWindows95の発売が予定されていた。
前バージョンWindows3.1は普及率が低く、主要OSであるMS-DOSは、PCのハードウェアリソースに対する要求は低かったため、 Windows95の発売はPCメーカーや、周辺機器メーカーにとっては大きなチャンスであった。 アイ・オー・データでも、メモリー専業から総合周辺機器へ転身する過程でハードディスクへの参入はそれ以前からも幾度となく検討されたが、ハードディスクの物理的な不良・破損のリスクが高いことを懸念し見送ってきた。
『ハードディスクは、ヘッドとディスク面の間隔が非常に狭い。半導体メモリーが主力の当時のアイ・オーにとって、可動部があって壊れやすいハードディスクへの参入は非常にリスクがありました。また当時は先行メーカーが高いシェアを握っていて新規参入は厳しい市場になると予測しました。Windows95がヒットしなければハードディスク事業への先行きは限られていました。』と当時ハードディスクの開発に携わった土田拓は語る。
 それでもWindows95の可能性に賭けた。 秋葉原では発売前日から長蛇の列ができ、午前0時の発売解禁をカウントダウンで迎え一気にWindows95ブームが巻き起こった。それまでパソコンに興味を持たなかった人たちにまで一気に消費層が広がって、パソコンビジネス全体のマーケットが一気に広がった。アイ・オー・データもその波にのりますます市場の要望にこたえる製品開発が進んだ。
それでもWindows95の可能性に賭けた。 秋葉原では発売前日から長蛇の列ができ、午前0時の発売解禁をカウントダウンで迎え一気にWindows95ブームが巻き起こった。それまでパソコンに興味を持たなかった人たちにまで一気に消費層が広がって、パソコンビジネス全体のマーケットが一気に広がった。アイ・オー・データもその波にのりますます市場の要望にこたえる製品開発が進んだ。
Windows95が浸透したことで、ユーザーの間では「少しでも早く、少しでも大容量」を望む声が高まった。 95年の「HDSシリーズ」のリリース以降、ハードディスク事業は順調に滑り出したが、その先には激しい価格競争が待っていた。『メモリー事業で得たPC 本体メーカーとのパイプやユーザーサポートのノウハウが強みとなり、激しい価格競争においても、一気に大きなシェアを得ることができました』と土田拓が語るように、ハードディスク事業においても短期でユーザーの支持を得たのである。
激戦の中で誕生した「i-CONNECT」(アイ・コネクト)
 一方で、PC98の寡占から、DOS/Vの台頭を迎え、パソコン業界は地殻変動の真只中だった。パソコンと周辺機器を繋ぐインターフェースもめまぐるしく変わった。SCSIが登場し、SCSI-2やSCSI-3、続いてウルトラSCSI、IDEに代わり、現在ではUSBやUSB2が主流になっている。
一方で、PC98の寡占から、DOS/Vの台頭を迎え、パソコン業界は地殻変動の真只中だった。パソコンと周辺機器を繋ぐインターフェースもめまぐるしく変わった。SCSIが登場し、SCSI-2やSCSI-3、続いてウルトラSCSI、IDEに代わり、現在ではUSBやUSB2が主流になっている。
このインターフェース技術の世代交代に当たってアイ・オー・データは2000年に独自の 「i- CONNECT」という新しいコンセプトを打ち出した。 「i- CONNECT」は、新規格が登場しても、ケーブルを追加するだけで対応でき、製品を陳腐化せずに済む。
時代の変化に、新たなコンセプトを取り入れることで「アイ・オーの製品なら安心」というユーザーの支持を得ることができた。 ハードディスクへの参入はメモリーのアイ・オーから、総合周辺機器のアイ・オーへ踏み出したきっかけとなった。
■記事から歴史を見る
・3月に地下鉄サリン事件が発生。
・野茂投手が大リーグで新人王に選ばれた。
・東証市場で1ドル79円75銭の円高を記録。
・東京臨海副都心と都心部を結ぶ新交通システム「ゆりかもめ」が開業。
・PHS(簡易型携帯電話システム)がサービスを開始。
・ポケベルで“会話”する「ベル友」 が流行語になる。


 商品一覧
商品一覧